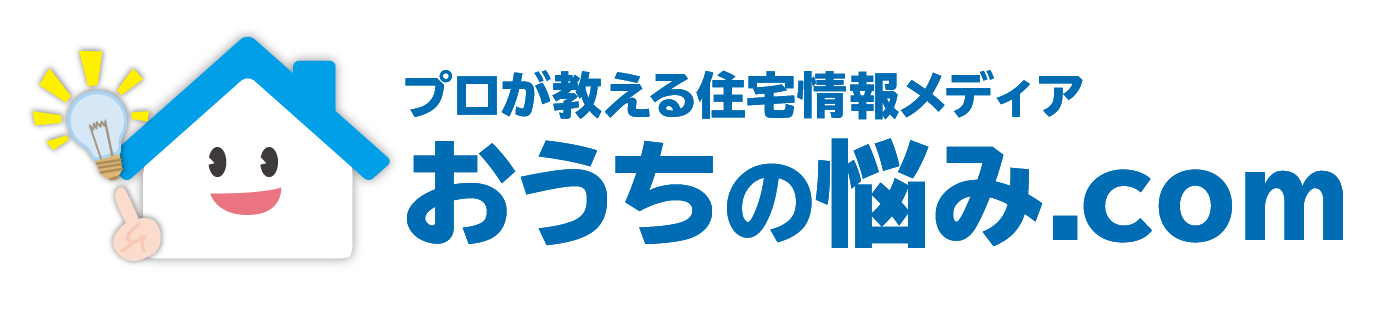注文住宅やマンション購入を検討していると「耐震等級」という言葉を目にすることがあります。
耐震等級とは、耐震性の高さを3つのレベルであらわしたもの。
ただし、巧妙な落とし穴もあるので数字だけに惑わされるのはとても危険です。
地震の被害にあってから「もっと耐震性の高い家にしておけば良かった…」と後悔するのは避けたいですよね。
この記事では、耐震等級の基礎知識、本当に地震に強い家に住むためのポイントを丸ごとお伝えします!
大切な家族を守るためにも、家づくりや賃貸物件選びの参考にしてみてくださいね。
「耐震等級」とは?

耐震等級とは、住宅の耐震性能を3段階レベルであらわしたものです。
耐震等級は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)で導入されている住宅性能表示制度の一つです。
住宅性能表示制度とは、耐震性・耐火性・防犯性などの10分野についてそれぞれランク付けしたもの。
耐震等級を取得するためには、専門の評価機関による現場検査が必要で、費用は15万円ほどかかります。
耐震等級と耐震基準の違い
耐震等級と似ている言葉に「耐震基準」というものがあります。
この2つには明確な違いがあります。
- 耐震基準=震度7の地震でも倒壊しない最低限の耐震性(建築基準法)
- 耐震等級=耐震基準以上の高い耐震性能を3段階で表示したもの(品確法住宅性能表示)
耐震基準は「建築基準法で定められている最低ライン」なので、施主がノータッチでも一定の水準を満たしたうえで建築されます。
一方、耐震等級は任意で取得する制度で、「より高い耐震性能を求めるハウスメーカーや施主がオプションでつける」といった位置付けになります。
「耐震等級」の等級ごとの違い

耐震等級には1~3までの3段階があり、数字が大きくなるほど耐震性は高くなります。
耐震等級の認定基準は、以下のとおりです。
| 耐震基準 | 建築基準法による最低限のライン |
| 耐震等級1 | 耐震基準と同等の耐震性 |
| 耐震等級2 | 耐震基準の1.25倍の耐震性 |
| 耐震等級3 | 耐震基準の1.5倍の耐震性 |
耐震等級1~3の違いを具体的に説明します。
耐震等級1「最低限の耐震性能」
耐震等級1は『建築基準法の耐震基準と同等』の耐震性で、震度7の地震で倒壊しないレベルの家です。
同じレベルなら「耐震等級1」と表示する必要はないと思われるかもしれませんが、耐震等級を取得するためには通常は行わない専門機関による現場の立ち入り検査があります。
したがって、住宅性能表示を取得していない家より、耐震等級1であっても住宅性能表示を取得している家の方が安心できるといえるでしょう。
また、耐震等級1を取得していると地震保険が割引される保険会社も多いです。
耐震等級2「耐震等級1の1.25倍の耐震強度」
耐震等級2は、耐震基準の1.25倍の耐震強度です。
これは学校や病院など『避難場所として指定されている建物と同等』の耐震性です。
「長期優良住宅」の認定基準は、耐震等級2以上を取得していることが条件となります。
長期優良住宅の認定を受けると、
- 住宅ローン控除、固定資産税の減税
- 新築、リフォーム時の補助金制度
など、住宅を維持するためにかかる資金が優遇されるというメリットがありますよ。
耐震等級3「耐震等級1の1.5倍の耐震強度」
耐震等級3は、耐震基準の1.5倍の耐震強度です。
これは警察署や消防署など『防災の拠点となる建物と同等』の耐震性です。
建築基準法による耐震基準は「震度7の地震で倒壊しない」となっていますが、とはいえ建物が無傷で済むわけではありません。
倒壊しなかったとしても、損壊が大きければ修繕をしないと住むことができないので、震災後すぐにはいつもどおりの生活に戻れないことも…。
また、一度の大地震には耐えられたとしても、熊本地震のように震度7の地震が連続して起こってしまった場合は、倒壊のおそれもあります。
 引用:読売新聞(防災ニッポン)
引用:読売新聞(防災ニッポン)
日本は地震がとても多いので、地震による被害を少しでも減らすためにも、耐震等級3を標準にしているハウスメーカーや工務店も増えてきています。
地震後の生活まで守ることを考えるなら、耐震等級3の家が安心だといえるでしょう。
調べ方 | 耐震等級はどこに書いてある?

「そもそも耐震等級ってどこに書いてあるの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
そこで、耐震等級の調べ方についてお伝えします。
【戸建住宅の場合】住宅性能評価書を確認する
戸建て住宅の場合、「住宅性能評価書」という書類に耐震等級について記載されています。
 参考:国土交通省
参考:国土交通省
「住宅性能評価書」と書かれた表紙を一番上にして、冊子のようになっています。
その中の「耐震等級」という項目をチェックしてください。
耐震等級には以下の二種類あります。
- 構造躯体の倒壊等防止
- 構造躯体の損壊防止
『構造躯体の倒壊等防止』の項目が、耐震等級のランクとなります。
【マンションの場合】不動産会社に確認をする
マンションの場合、不動産会社に確認するのがもっともスムーズです。
なお、中古物件や賃貸物件などのすでに建物が完成しているマンションは、建築時期から耐震性のレベルを予想できます。
ポイントは次の3つです。
- 建築基準法の「耐震基準」が大幅に改正されたのは1981年。
つまり、それ以前に建てられた古いマンションは旧耐震基準であり、耐震等級1レベルを満たしていない可能性が高い。 - 「耐震等級」という評価制度は2000年に登場した。
よって、2000年以降に建てられた比較的新しいマンションであれば、耐震等級を取得している可能性がある。 - 古い建物でも「既存住宅性能評価」を受けることで耐震等級を取得できる。
そのため、建築年が2000年以前の古いマンションであっても、任意で耐震等級を取得している可能性がある。
築年数とこれらを照らし合わせ、ある程度の耐震性を予想することができます。
しかし、そのマンションが『本当に耐震等級を取得しているか』『制震・免震構造は採用されているのか』などはわからないため、正確な耐震性能は不動産会社に確認してくださいね。
【耐震等級が不明の場合】登録住宅性能評価機関に作成を依頼する
住宅性能評価書がなく、耐震等級がわからないときは、登録住宅評価機関に依頼して新たに耐震等級を取得することができます。
【耐震等級の評価を受ける流れ】
- 専門機関に連絡する
(住宅性能評価・表示協会) - 建物のチェックを受ける
- 住宅性能評価書をもらう
既存住宅の場合、耐震等級取得にかかる費用はおよそ10万円前後です。
木造二階建ての落とし穴

あなたが建てたい家が木造二階建てなら、注意すべき重要なポイントが3つあります。
- 構造計算の種類は2つある
- 4号特例に要注意
- 耐震等級3「相当」のリスク
これらは、耐震等級の数字だけに惑わされないようにするための大事な注意点になります。
それぞれ詳しく説明します。
構造計算の種類は2つある
建物の正確な耐震性を知る方法として、「構造計算」というものがあります。
構造計算の種類は次の2種類です。
- 許容応力度計算による構造計算
- 壁量計算による構造計算
重要なのは「許容応力度計算(きょようおうりょくどけいさん)」の方です。
この2つがどのように違うのか説明します。
許容応力度計算による構造計算
まずは、許容応力度計算による構造計算についてです。
構造計算とは、建築構造物・土木構造物などが、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重などに対して、構造物がどのように変形し、構造物にどのような応力が発生するのかを計算することである。また、構造物がそのような変形や応力に耐えられるのかを判定することも含まれる。構造物の安全性や使用性を確認するのが目的である。最終的には、構造計算書として、A4の紙で100~5000枚程度にまとめられる –Wikipedia
簡単にいうと、『屋根に6tの積雪がある状態で地震が起きたときの耐震力』『それぞれの階数ごとの強度』『地震で建物が傾く度合い』など、ありとあらゆるケースを想定したうえで耐震性を厳密に計算する方法です。
許容応力度計算による構造計算は、建築士が業務の片手間で簡単にできるようなものではなく、専門家が時間をかけて複雑かつ緻密な計算をおこないます。
算出された計算書はA4用紙100~5000枚と膨大な量になり、費用も20~30万円ほどかかります。
高額にはなりますが、建物の耐震性を正確にあらわした信頼性の高いものになりますので、三階建ての木造住宅やRC造の建物を建てるときは、建築確認申請時にこの構造計算書の提出を義務付けています。
建築業界では、単に「構造計算」という場合はこちらの許容応力度計算による構造計算のことを指しています。
壁量計算による構造計算
壁量計算による構造計算とは、主に耐力壁の量だけに注目した簡易な計算方法のことです。
『壁の枚数は何枚か?』『屋根は重いか?軽いか?』など非常に簡単なもので、計算書はA3用紙1枚にまとめられる程度です。また、費用もかかりません。
一般的に木造二階建ての住宅は、こちらの壁量計算による構造計算がほとんどです。
しかし、建物の形状を踏まえたこまかい計算はされていないため、正確な耐震性をあらわしているとはいえません。
ハウスメーカーの担当者が「この建物はきちんと構造計算しているので安心です!」という言い方をすることもあります。
『許容応力度計算』『壁量計算』どちらも”構造計算”に間違いはないのですが、重要なのは許容応力度計算による構造計算の方です。
そのような話をされたら「それはどちらの構造計算ですか?」と確認してみてくださいね。
「4号特例」に要注意
建築基準法では、木造二階建て以下の建物を「4号建築物」と呼んでいます。
そして、家を建てるときの建築確認申請時には「4号特例」という以下のような特例があります。
- 4号建築物は、許容応力度計算による構造計算をしなくてもよい
- 4号建築物は、壁量計算による構造計算書の提出を省略してもよい
この記事内で、許容応力度計算による構造計算が重要であることを述べましたが、簡単にいえば木造住宅(二階建て以下)はその構造計算をしなくてよいということです。
しかも、簡易な壁量計算でさえも提出を省略できるとされいます。
この特例は、新築住宅のほとんどが二階建て木造住宅であることから、建築確認申請に時間がかかりすぎないように簡略化して手間を省くために設けられたものです。
壁量計算による構造計算は、建築士の裁量でおこなうことを義務付けてはいますが、提出しなければチェックはできませんので、確認申請の審査で実際の耐震性を知ることはできません。
過去に大地震が起きた際、耐震等級2の長期優良住宅が倒壊した例がありました。
原因を探るために、あらためて許容応力度計算による構造計算をしたところ、その建物は建築基準法の耐震基準すら満たしていませんでした。
壁量計算が簡単な計算であるうえ、4号特例によって提出が義務化されていないため壁量計算をしていたかどうかも不明です。
4号特例は、このような事態を起こす危険な落とし穴です。
あなたの家や大切な家族を守るためには、自主的に許容応力度計算による構造計算をおこなうことが有効です。
耐震等級3「相当」のリスク
注文住宅ハウスメーカーが、耐震等級3「相当」と表示しているのを目にすることがあります。
これは、耐震等級3の建物と同じ間取り、同じ材料を使用して建築はするけれども、あえて耐震等級を取得せず、取得にかかる費用を建物価格に還元する目的があります。
施主からしてみれば「同じくらいの耐震性なら安い方がいい」と思いますよね。
しかし、耐震等級を取得していないため、法律上では耐震基準のみクリアした建物になります。
そのため、長期優良住宅のローン減税や補助金、地震保険の優遇も対象外となり、将来売却するときにも「耐震等級3」という付加価値をつけられず、結果的に売却価格が下がる可能性もあります。
さらに、費用をおさえるために構造計算をおこなっていないので、本当の耐震性を証明する書類もありません。
この場合、自主的に許容応力度計算による構造計算をおこなうことが有効な方法だといえます。
住宅は決して安い買い物ではありません。費用をおさえるために、耐震等級3「相当」の家にする選択肢もあるでしょう。
しかし、高い買い物だからこそ本当に安心できる家づくりを考えていくことが大切です。
地震に強い家選びのポイント

家の耐震性は、基礎が頑丈であることはもちろん、家の形や使われている材料によっても変わります。
そこで、地震に強い家選びの4つのポイントをお伝えします。
覚えておけば家づくりに役立つはずです。
耐震性能が良いのは軽量な屋根
まず注目すべきポイントは、屋根の重さです。
屋根が重いと建物の重心が高くなるため、地震で大きく揺れる耐震性の低い家になってしまいます。
重量のある瓦屋根はできるだけ避け、スレートやガルバリウム鋼鈑などの軽い屋根材の家を選ぶのがよいでしょう。
日本の住宅の特徴のひとつに、屋根瓦があります。 新築で家を建てる時やリフォームをする時に屋根瓦が候補に挙がっているのであれば、まずは瓦の特徴やメリット・デメリットを把握することから始めることが大切! この記事[…]
耐力壁が多い
耐力壁(たいりょくへき・たいりょくかべ)とは、地震力に抵抗できる強度のある壁のことです。
柱だけでは耐えきれない地震の揺れを、強い壁として支えることで、より耐震性が高まります。
大きな窓や吹き抜けのある開放的な間取りは、耐力壁が少なくなるため要注意。
地震に強い家ほど、耐力壁がたくさん使われています。
中古住宅を探していると、『新耐震基準』という言葉を目にすることがありますよね。 新耐震基準は、建物の安全性を見分けるうえで重要なポイント。 「一体何が新しいの?」「どのくらいの耐震性なの?」と、よく分からない人も多いのではないで[…]
耐力壁&耐震金物がバランスよく配置されている
耐力壁は、バランスよく配置してこそ使う意味があります。
必要壁量を満たしていてもバランスが悪ければ、耐震性は低くなってしまうでしょう。
接合部に使われている耐震金物も同様です。
地震に強い家に住むためには、各部屋の一部に、耐力壁と耐震金物がバランスよく配置されているかをチェックすることが大切です。
床の耐震性能もしっかりしている
地震に強い家は、床の強度も高いです。
従来、木造住宅は床の下に根太(ねだ)という横木を打ち付け、その上に薄い合板(12mm)を敷いて床をつくっています。
しかし根太は、水平方向の地震力に弱いため、地震の横揺れで床がゆがんで崩れてしまう可能性もあります。
そこで注目されているのが、「剛床工法(ごうゆかこうほう)」(通称:根太レス工法)と呼ばれる、床の耐震性能を高めた施工方法です。
剛床工法とは、根太をなくしてその代わりに厚さのある構造用合板(24mm以上)を直接太い木材に打ち付ける工法のこと。
 引用:敷島住宅
引用:敷島住宅
線ではなく面で支えることにより、地震で変形しにくい強い床になります。
床の施工方法が「剛床工法(根太レス工法)」であれば、地震に強い家といえるでしょう。
まとめ
耐震等級には3段階のレベルがあり、数字が上がるほど耐震性能は高くなります。
【耐震等級の基準】
| 耐震基準 | 建築基準法による最低限のライン |
| 耐震等級1 | 耐震基準と同等の耐震性 |
| 耐震等級2 | 耐震基準の1.25倍の耐震性 |
| 耐震等級3 | 耐震基準の1.5倍の耐震性 |
【木造二階建ての注意点】
- 構造計算の種類が「許容応力度計算」なら安心
- 構造計算書の提出を省く「4号特例」に要注意
- 耐震等級3「相当」は各種優遇が受けられない
いざというとき、あなたの家や大切な家族を守るために耐震性は重要です。
耐震等級の数字だけに惑わされることなく、本当の耐震性を知って安心できる家づくりをしてくださいね。
【この記事の次におすすめしたい記事】
「家を建てて満足していますか?」と調査したところ、なんと2人に1人が後悔しているという結果でした。 住宅ローンが大変で生活が苦しい 間取りや設備に失敗して家事が不便… 会社選びに失敗してアフターフォローが最悪! せっかく建てたの[…]
本ページはプロモーションが含まれています これからの人生を過ごすために購入する、夢の新築一戸建。家は、一生のうちで一番大きなお買い物です。 たくさんのお金と時間を費やし、長期間住宅ローンを返すことにな[…]