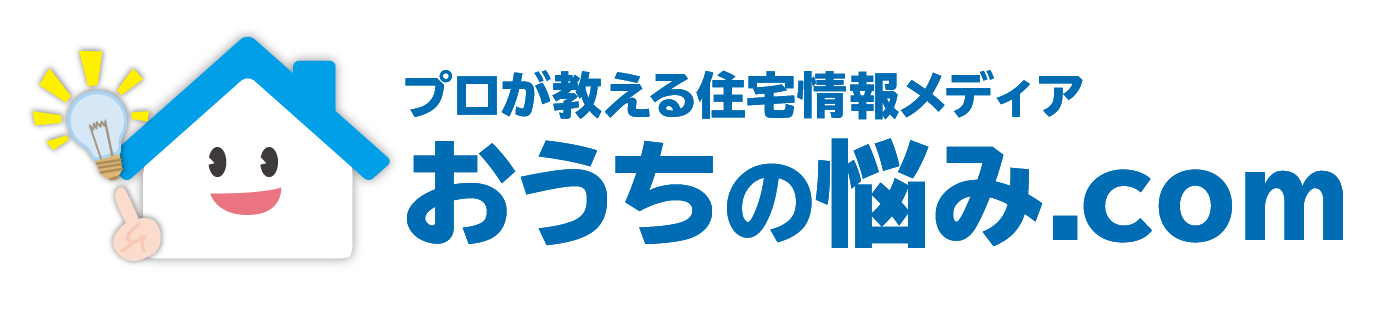長期優良住宅とは国交省が一定の基準を定めて、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がとられた住宅を認定する制度です。
『スクラップ&ビルド(建てては壊す)』といった従来の考え方から、『いいものをつくって、キチンと手入れして、長く大切にする』考え方に変えていくという発想に基づいています。
この記事で長期優良住宅の特徴やメリット、デメリット、申請方法を理解し、購入するときの参考にしてくださいね。
 【記事監修】
【記事監修】嵯峨根 拓未(株式会社ドレメ 取締役(現場責任者))
資格:一級建築士、宅地建物取引士
戸建て住宅、ヴィラ、グランピング等幅広い物件の現場を経験。
実際の経験を基に、あなたのおうちの悩みを解決します
長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、『長期優良住宅の普及促進に関する法律』に基づき、国土交通省が新築・増改築住宅を対象に認定する住宅のことで、その名の通り住宅を良好な状態で長期で使用することが目的。
国からの優良であるという認定をもらうために多少の建築上の決まりごとに従う必要がありますが、そのぶん金銭的メリットはたくさんあります。
長期優良住宅に求められる5つの措置
長期優良住宅は、大きく分けて下記5つの措置が講じられた住宅を指します。
- 長期に使用するための構造および設備を有している
- 居住環境などへの配慮をおこなっていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
- 災害への配慮を行っていること
一戸建ての住宅はもちろん、マンションのような共同住宅や店舗等の併用住宅も対象です。
認定には着工前の手続きと工事完了後に検査があり、両方をクリアする必要があります。
2022年に法改正があり、変更は以下の4点。
地すべりの可能性のある区域、急傾斜で崩壊の可能性のある区域、開発行為などによって土砂災害の危険性のある区域について長期優良住宅を認定しない地域が決められました。
共同住宅(たとえばマンション)では区分所有者(一戸を保有する所有者)が各自申請
→管理組合が一括して申請可能
住宅性能評価を行う民間機関と、長期優良住宅であることの確認機関へ各々申請
→ 民間機関が住宅性能評価を行うのと同時に、長期優良住宅であることの確認が行えるようになりました。
長期優良住宅の断熱性基準が断熱性等級4 → ZEH(ゼッチ)基準へ変更
ZEHとはゼロ・エネルギー・ハウスの略で断熱性だけでなく、省エネ性能の高い設備、太陽光などエネルギーを作り出す設備を導入してエネルギー収支ゼロを目指しています。
長期優良住宅の目的や意味
長期優良住宅の本来の目的は、建てた住宅をメンテナンスして長く使用することですが、自分の住宅が国が優良と認定する住宅になることで、税控除やローン金利など金銭面のメリットを受けることができます。
認定条件にはメンテナンスの項目もあるため、住宅をリセールするときも‘’認定されている”住宅は、”認定されていない”住宅と比べると有利になることが多くあります。
長期優良住宅制度の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるには10項目の認定基準をクリアして申請する必要があります。
以下の要件を満たした建物とメンテナンスの計画を用意したうえで、事前に申請手続きをする必要があります。
耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
建築時に認定基準にみあった耐震性の建物を建てなければいけません。
そのため、以下のいずれかの措置が必須になります。
- 建築時に耐震等級(倒壊等防止)等級2
- または耐震特級(倒壊等防止)等級1かつ安全限界時の眉間変形を1/100(木造の場合は1/40)以下
- 品確法に定める免震建築物
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
認定基準では断熱性等性能等級4の基準に沿った建物(新築)である必要があります。
建物の躯体構造(木造や鉄筋コンクリート造等)部位(屋根、壁、床、土間等)に断熱抵抗の規定値が細かく定められています。
このほかに開口部の規定、結露防止の規定が存在します。
維持管理・更新の容易性
認定基準では維持管理対策等級の等級3、更新対策の等級3である必要があります。
維持管理対策とは給排水やガス管について躯体に影響されずに点検、維持管理、補修、更新が出来るように一定の基準を定めたものです。
具体的には水回りの配管をコンクリートに埋め込まない、清掃に支障がないように設置が必要です。
劣化対策
認定基準では劣化対策等級3の基準に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合していなくてはなりません。
具体的には
- 木造・鉄骨造では床下空間の高さ、床下・小屋裏の点検口の設置を行う
- 鉄筋コンクリート造では水セメント比やかぶり厚さに規定に準ずる
- 鉄骨造では梁や柱に防さびの加工を行う
といった内容があります。
住戸面積
一戸建ての住宅については75㎡以上。
共同住宅については55㎡以上である必要があります。
地域によって、個別に定めていることもあるため、所管行政機関や住宅メーカーに問い合わせてみましょう。
居住環境
地区計画、景観計画、条例による町なみ等の計画、建築協定、景観協定等が区域内にある場合はこれらの内容と調和を図るとされており、建築計画のある所管行機関に確認する必要があります。
維持保全管理
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の侵入を防止する部分
- 給水・排水のための設備
上記3点は定期的な点検を行うなど、補修に関する計画と実施が必要です。
また、通常時であっても10年に1度、地震や台風などの自然災害が起きたときは臨時点検を実施しましょう。
バリアフリー性(共同住宅等のみ)
高齢者等配慮対策等級(等級3)が必要です。
寝室とトイレの配置、段差の解消、手すりや階段の規定、車いすを想定した通路や出入り口の規定等があります。
可変性(共同住宅または長屋のみ)
躯体天井高さ2,650mm以上(新築)である必要があります。
災害配慮
災害発生のリスクのある地域については、そのリスクの高さに応じて所管行政庁が定めた措置を講じます。
建築計画の行政機関や住宅メーカーに問い合わせてみましょう。
長期優良住宅のメリット・デメリット

国交省お墨付きの優良住宅と認定される長期優良住宅ですが、認定取得には事前申請が必要で、要件を満たすためにはコストがかかるケースもあります。
しかし、かかった手間以上のメリットも受けることが可能。
ここではメリット・デメリットを項目別に解説していきます。
【メリット】住宅ローンの金利が引き下げられる
住宅ローンの支払いが楽になります。
住宅は大きな買い物、金利が引き下がるメリットは大きいと言えるでしょう。
フラット35
フラット35は住宅ローンを35年間固定金利にて返済するプラン
長期優良住宅ではなくとも利用でき、取り扱う金融機関も豊富で金融機関によって金利もまちまちです。
多彩なラインナップがあり、それぞれ金利が変わってきます。
例)買取型:自己資金の割合で金利が変動
地域連携型:Uターンや子育て支援を目的に補助金交付している場合金利優遇
フラット35S
長期優良住宅の認定を受けた住宅が利用できるプランである『フラット35S』。
フラット35の金利を一定期間引き下げる効果があるので使わない手はないですね。
フラット35Sには2種類のプランがあります。
- フラット35S Aプラン フラット35の借入金利から、さらに10年間−0.25%
- フラット35S Bプラン フラット35の借入金利から、さらに5年間-0.25%
*金利マイナス効果は初年より適用。
*予算枠があり、受付終了になるケースがあります。
*中古住宅購入に利用されるフラット35リノベとの併用利用ができません。
『フラット35S』の毎月の返済額・総返済額の試算
【試算例】借入金額3,000万円(融資率90%以下)、元利均等
ボーナス返済なし、借入金利年1.5%の場合
フラット35S金利Aプランならフラット35と比べて、総返済額が約73万円お得です。
フラット35S金利Bプランならフラット35と比べて、総返済額が約39万円お得です。
| フラット35 | フラット35S(金利Aプラン) | フラット35S(金利Bプラン) | |||
| 借入金利 | 全期間
年1.5% |
当初10年間年1.25% | 11年目以降
年1.5% |
当初5年間 年1.25% | 6年目以降 年1.5% |
| 毎月の返済額 | 期間 | 当初10年間 | 11年目以降 | 当初5年間 | 6年目以降 |
| 総返済額 | 91,855円 | 88,225円 | 90,857円 | 88,225円 | 91,368円 |
| フラット35との比較 | ― | ▲730,938 | ▲393,232 | ||
備試算は2022年5月時点の金利を採用しています。試算は概算です。
審査がありますので、金融機関や条件によっては審査が通らないケースがあります。
長期優良住宅であればフラット50を利用することも可能で、最長返済期間を50年に設定できます。
【メリット】税制優遇措置がある(住宅ローン控除)
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは住宅の購入やリフォームのために住宅ローンを組んだ人に対して、本来払うべき税金が減額される制度。
サラリーマンの方であれば、収めた所得税と住民税から年末調整を経て一部戻ってくる優遇措置です。
住宅ローンを組むほとんどの人が住宅ローン控除を利用します。長期優良住宅は、住宅ローン控除についても優位性があります。
◇長期優良住宅と一般住宅の比較表
| 住宅の種類 | 一般住宅(省エネ基準適合住宅) | 長期優良住宅 |
| 限度額 | 4000万円 | 5000万円 |
| 控除期間 | 13年 | 13年 |
| 控除率 | 0.7% | 0.7% |
| 最大控除額 | 364万 | 455万 |
| 年間控除限度額 | 28万 | 35万 |
所得税控除
新築は住宅ローンを組んで購入される方が大半だと思われますが、長期優良住宅であればローンを組まなくても投資型減税を用いて、所得税から控除をうけることができます。
| 控除限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 650万 | 1年間 | 10% | 65万円 |
控除額は性能評価強化費用相当額(一般の住宅から長期優良住宅にすることにかかる費用)によって変動します。
工務店・住宅メーカーに確認してみましょう。
登録免許税の軽減
不動産登記制度は、建物の状態、所有者、権利の状態を法務局に登録する制度。
第3者に対して自分の保有であることを主張できます。
新築で住宅を建てると保存登記(一番最初の登録の登記)されますが、この時に登録免許税がかかります。
長期優良住宅では税率の部分が0.1%で一般住宅の0.15%と比べて優遇され、ここでも若干ですがお得感がありますね。
固定資産税
住宅を保有すると、所有者に固定資産税が課税されます。
一定の要件を満たすと固定資産税が1/2に軽減されますが長期優良住宅では減税の期間が優遇されます。
| 住宅の種類 | 戸建て | マンション |
| 一般の住宅 | 3年間 | 5円間 |
| 長期優良住宅 | 5年間 | 7年間 |
補助金
長期優良住宅は地域型住宅グリーン化事業の補助金の対象となります。
補助金対象の要件
- 新築であること
- 木造であること、地元の木材を使用していること
- 国の採択を受けた施工業者であること
長期優良住については110万円~140万円
地域材加算、3世代同居加算、バリアフリー加算などがあります。
併用加算や加算上限額がありますので詳細はハウスメーカーや工務店にお問合せください。
1年ごとに補助金交付が決定されますので交付決定を確認し、税制、控除、補助金については都度変化しますので直近の情報をご確認ください。
【メリット】地震保険料が割引になる
技術的審査適合証、認定通知証を提出することによって地震保険料が割引になります。
技術的審査適合証は全国に123ある登録住宅性能評価機関が技術的審査をして、その適合証を所管行政庁に認定申請していきます。
登録住宅性能機関をお探しの方はこちらから
*一覧から検索 | 登録住宅性能評価機関 | 評価機関等の検索 | 評価機関等の検索[評価協会] (hyoukakyoukai.or.jp)
免振建築物・耐震等級3で50%の割引、耐震等級2で30%の割引が適用されます。
【メリット】売るときに価値が高くなる
ずばり、長期優良住宅の認定を受けていると、中古物件としてのリセールバリューは高くなります。
手間をかけて申請するだけあり、同条件で『長期優良住宅』と認定のとれていない住宅のどちらかを買うとしたら、結果は明らかです。
国交省の審査を受けての物件ですから、ある意味価値が担保されており購入者が安心して購入できます。
資産として運用される方にとってもインパクトのあるメリットであると思われます。
【デメリット】申請の準備に時間がかかる
着工前に所管行政庁に申請手続きが必要であるため、着工までにまず時間がかかります。
適合証の証明が必要な場合は、登録住宅性能評価機関に申請が必要なケースも出てきます。
工事が完了した後にも報告が必要です。
役所的な手続きを得るため2~3週間は見ておくことをおすすめします。
【デメリット】コストがかかる(建築コスト・申請コスト)
建築コスト
認定基準の要件を満たすために、グレードの高い設備や建材を利用した場合、想定外に建築コストがかさんでしまうケースも。
各項目に基準が設けられていますが、バリアフリー性や居住環境にある地域の特性でコスト増になるケースは見受けられます。
例えば、軽井沢のような避暑地で木目調をベースにした住宅しか認めないケースや日照権などで高さを制限されるケースなど。選ぶ際にどこまで認定基準を満たしているか事前に確認しておくことをおすすめします。
申請コスト
申請手数料がかかります。
行政機関によって変動がありますが、所管行政への申請と住宅性能評価機関への手数料で10万円ほどかかるでしょう。
住宅メーカーに申請書類を一任する場合も20万円程の手数料が必要になります。
【デメリット】定期的にメンテナンスを行う必要がある
定期メンテナンスは、維持保全計画書に沿って行われます。
定期的に点検、調査、修繕、改良を繰り返します。
- 維持保全の期間は30年以上
- 点検時期の間隔は10年以内
- 地震・台風時に臨時点検の実施
- 点検の結果を踏まえ、必要に応じて調査、修繕または改良を実施
- 住宅の劣化状況に応じて内容を見直しする
都度コストもかかりますが、長期的に活用するには必要で、ほったらかしにしておいて
後から高額なコストがかかるよりは長期目線では安心して暮らすことができます。
維持保全計画が実施されない場合は長期優良住宅の認定が取り消されることもありますのでご注意ください。
長期優良住宅の申請方法

所管行政庁に申請書、必要書類をそろえて申請し交付を受けます。
そのために、申請に必要な書類のひとつである『長期使用構造であることの確認書』の交付を受ける必要があります。
申請手続きは、施工業者などが代理で行うことも可能です。
着工は長期使用構造の認定通知の交付を受けてからになります。
長期使用構造であるかの確認について
登録住宅性能評価機関に申請をし確認書の交付を受けます。
申請先のリンクはこちらから
*一覧から検索 | 登録住宅性能評価機関 | 評価機関等の検索 | 評価機関等の検索[評価協会] (hyoukakyoukai.or.jp)
長期優良住宅の認定申請について
申請先は建築予定地の市役所であることが多いですが、規模の小さい町村関係は都道府県庁に提出することがほとんどです。
下記リンク先を参照ください。
長期優良住宅建築等計画の認定 (hyoukakyoukai.or.jp)
申請の流れ
①事前調査・準備
メーカーや工務店に相談し認定に必要な要件の確認。
基準を満たすためのコストなどを事前に相談します。
以下の書類を用意します。
- 長期使用構造できることの確認申請書
- 設計の内容説明書とその添付資料
- 添付図面
- 委任状
- その他審査に必要な書類
②申請書提出
③審査の結果を待ち、質疑問い合わせに回答
④入金手続き
⑤確認書の受領
長期優良住宅を建てたいならプロにに相談
ハウスメーカーは、各社それぞれが素敵な提案をしてくれます。
話を聞き、考えれば考えるほどどの会社が本当にいいのかわからず、迷ってしまう方も少なくありません。
そんな方には、「SUUMO」が提供している建築会社選び講座がおすすめ。
住宅建築アドバイザーがあなたのライフスタイルや状況などを聞き、フラットな目線で総合的な判断をしたうえで無料で会社選びのコツを教えてくれます。
- 維持費の抑えた家を建てる方法は?
- ハウスメーカーと工務店どっちがいい?
- 建築会社はどうやって選べばいいの?
- 理想の家を建ててくれる建築会社を見つけたい!
- 第三者の目線でアドバイスが欲しい
- カタログやインターネットだけでは判断できない
どれか1つでも当てはまる方にはオススメできる講座です。


全国に80か所以上ある店舗か、インターネットを使って自宅でも受講できます。
プロの目線から本当にあなたに合った会社を紹介してもらうこともできます。
完全無料で、個別相談に対応してくれるので、本気で良い家を建てたい方は是非チェックしてみてくださいね!
まとめ
長期優良住宅は価値の高い住宅であることは間違いありません。
国交省のお墨付きの認定住宅となるので、本人のみならず、第三者からみても長期的な安心感がありおおきなインパクトがあるでしょう。
認定実績も毎年10万戸(新築)ずつ増えてきており、検討する価値がありです。
選んだ住宅によって認定にかかる手間とコスト、年収によって金利や税控除が変わりますが、建てる前にシミュレーションする事ができます。
工務店やハウスメーカーによくよく相談して進めていくことをおすすめします。
見積もりをする住宅が決まったらメリット・デメリットを具体化していくのがよいでしょう。
コスト的なメリット・デメリットは計算で出てきますので、このコストと手間・将来にわたる安心感をてんびんにかけて行くとイメージが膨らみやすいですよ。
マイホームは一生に一度の大きな買い物。
後悔のない選択が出来るよう、この記事が役に立つようであれば幸いです!
マイホームづくりは、くれぐれも慎重に…
「家を建てて満足していますか?」と調査したところ、なんと2人に1人が後悔しているという結果でした。 住宅ローンが大変で生活が苦しい 間取りや設備に失敗して家事が不便… 会社選びに失敗してアフターフォローが最悪! せっかく建てたの[…]