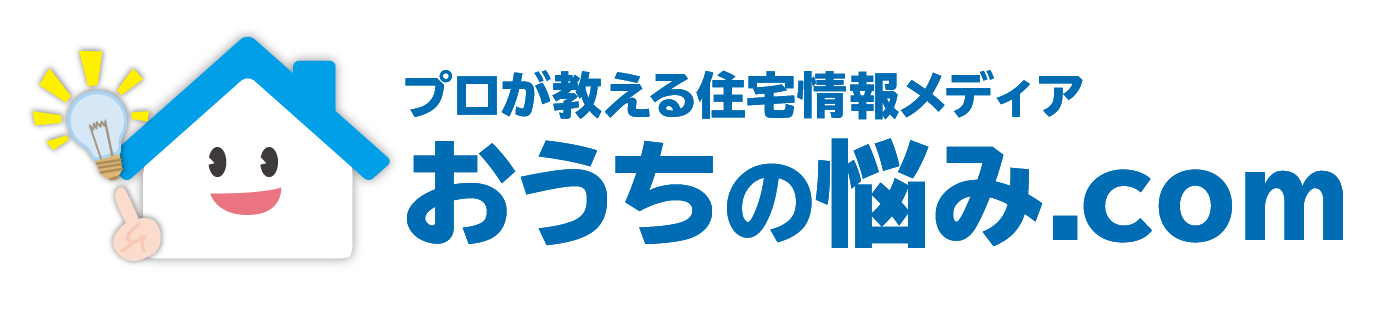『返済負担率』という言葉をご存じでしょうか。
これは、住宅ローンの借り入れを検討しているときによく目にするキーワードのひとつ。
この『返済負担率』とは、現在の年収でどのくらいの額を借り入れるのが適正かを判断する指標となるものです。
この記事では、
- 適正な返済負担率は何%?
- 無理のない返済負担率とは?
- 返済負担率以外に考えておくこと
など、住宅ローンを組む前に浮かんでくる疑問点や、事前に知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
住宅ローンの返済負担率とは?

返済負担率とは、年収に対してローンの年間返済額が占める割合のことで、『返済率』や『返済比率』『年収負担率』ともいわれています。
金融機関では、住宅ローンの借入額(融資額)を審査するとき、申請者の年収や、別の借り入れの有無などの情報から返済負担率を算出し、合否の判断をするというのが一連の流れ。
一般的には、返済負担率が額面年収の25〜35%程度に収まるかどうかが基準になることが多いです。
返済負担率は次の式で計算することができます。
目安にするためにも、一度ご自身の年収で計算をしてみましょう。
理想の返済負担率は?

実を言うと、生活に支障をきたすことなく、無理のない暮らしができる『理想の返済負担率』と、金融機関の審査基準である借り入れ目安の返済比率は異なるものなのです。
理想は手取り年収の20%
金融機関の住宅ローン審査に合格する返済負担率は額面年収の25〜35%と先述しましたが、実際のところ、生活面での負担がなく返済できる理想の返済負担率は、手取り年収の20%といわれています。
額面年収と手取り年収には、大まかに計算して約20%ほどの差があるため、金融機関の指標と理想の返済負担率には、大きな差があることがわかりますね。
理想の返済負担率が20%であるという理由は、以下の2つ。
- 返済期間中に家計の収支が変動する可能性が高い
- 住宅ローンの返済以外に家にかかる支出が大きくなっていく
借入期間が数十年以上と長期化する住宅ローン。
返済が残っている間に、子どもの教育費が増えたり、病気や不慮の事故で予期せず収入が減ってしまったりと、不測の事態も起こりうるもの。
それに加えて持ち家の場合は、経年劣化を避けては通れないので、補修や点検など住宅の維持費もかかってしまいます。
住宅ローンの返済負担率を低く見積もることで、こうした家計の負担にも余裕をもって対応できるような借入金額を算出するようにしましょう。
金融機関での目安は25%~35%
先ほども触れましたが、金融機関の住宅ローン審査の合否の判断基準となる返済負担率は額面年収の25〜35%です。
ここでの返済負担率は、金融機関や借り主の年収によって変わってくるもの。
どうして、金融機関が提示している返済負担率と理想の返済負担率との間にこうした差があるのでしょうか。
答えはいたってシンプルで、金融機関が『返済できる信用と経済力があるか』というポイントだけを見ているからです。
つまり、金融機関の示す借入可能額は、借り主の希望するライフスタイルや、思い描いている人生計画などは考慮していないということになります。
こうした点には注意が必要と言えるでしょう。
住宅ローンの返済に毎月追われ、外食や旅行にも行けず、人生を楽しむことができない・・・となってしまっては意味がありません。
金融機関の目安に従って融資可能額の上限いっぱい借りることは避け、理想の返済負担率を参考に、余裕のある借入額で返済計画を立てましょう!
フラット35は額面年収の条件付き
住宅金融支援機構と金融機関が提携して提供する住宅ローン商品、フラット35では、返済負担率に関して明確な審査基準が設けられています。
額面年収400万円未満・・・返済負担率30%以下
額面年収400万円以上・・・返済負担率35%以下
とはいえ、あくまでこれらも金融機関が示している返済負担率。
そのため、他の住宅ローン商品と同様に「自分にとって理想の返済負担率」は、今後のライフプランや急な出費を考慮したうえで考えていく必要があることに変わりはありません。
返済負担率以外にも考慮すべき指標

ここからは、住宅ローンの借入額を検討するときに大切な、返済負担率以外の指標について解説します。
完済年齢
完済年齢とは、住宅ローンを返済し終わる年齢のこと。
例えば、30歳で借入期間が35年の場合は65歳、40歳で借入期間35年の場合は75歳となります。
結論からいうと、年金生活が始まる前に住宅ローンを完済するのが理想。
つまり、住宅ローンの完済年齢は、65歳に設定しておくことが望ましいのです。
理由は、もし完済年齢を75歳に設定した場合、残りの10年は年金収入から住宅ローンを返済しなければならないからです。
とはいえローンの返済期間を短くしてしまうと、毎月の返済額が増えることになるので、理想の返済負担率の範囲で収めることが難しくなってしまいます。
返済負担率と完済年齢のバランスを考え、頭金を貯めるといった準備をしっかりと整えてから融資を受けるようにしましょう。
年収倍率
返済負担率と同様に、『年収倍率』という言葉を見かけたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
年収倍率とは、年収の何倍程度の借り入れをするかを示した倍率のことです。
一般的に、理想の年収倍率は「5倍」といわれており、例えば、世帯年収が400万円の人であれば、2,000万円の借入が理想ということになります。
しかし、2019年度のフラット35利用者調査を見ると、注文住宅の年収倍率の全国平均は7.3倍。
年収の7倍ほどの家を購入している人が多いということですね。
返済負担率の視点からみると、「年収の7倍の家を買って、返済負担率が大きくなるのでは!?」と思ってしまいそうですが、ここで忘れてはいけない点は、購入金額には「頭金」が含まれているということです。
頭金を多く支払っていれば、そのぶん住宅ローン借入額は購入金額よりも少なくなるため、返済負担率も下がることになります。
返済負担率から借入額を決めるときの注意点

返済負担率から借入額を決めるときは、どのような点に気をつければよいのかを見ていきましょう。
家計状況をによって適正な返済負担率は変わる
家庭によって生活費や教育費などが違うように、理想の返済負担率も家庭ごとに異なります。
収入や生活費や教育費、貯金などを考慮した上で、借入後も無理なく生活できるように設定することが大切です。
毎月支払っている家賃や家計から、月ごとにどのくらいの金額を住宅にかけられるかを計算してみましょう。
住宅以外のローン返済額も含めて考える
自動車ローンや奨学金など、住宅ローン以外の借入がある場合や、今後借入をする場合は、それらの合計がいくらになるのかをあらかじめ算出しておきましょう。
住宅ローンだけを見て余裕があったとしても、その他の借り入れも含めて考えると、返済の負担を大きく感じる場合があります。
また、他の借入をしている場合は、まずは他の借入を貯金等で完済したあと、住宅ローンの申し込みをした方が良いケースがあることも覚えておきましょう。
その他の関連費用も考慮する
返済負担率は、住宅関連の費用のうち住宅ローンの返済部分しか考慮されていません。
しかし、住宅の購入には、物件本体の費用のほか、手続きにかかる諸費用が必要で、これらは原則、住宅ローンではなく現金での支払いとなります。
また、住宅ローンの返済以外にも固定資産税といった税金がかかり、マンションの場合は修繕積立金や管理費などの支払いも定期的に発生します。
加えて、新居に置く家具を買いそろえたり、家電を買い買えたりといった費用が必要になることも・・・。
住宅関連だけを見ても、様々な費用がかかることがわかりますよね。
これらの支出も考慮したうえで、住宅ローンの返済計画を立てるようにしましょう。
まとめ
今回は、住宅ローンの返済負担率について解説しました。
返済負担率への理解が深まり、疑問が解消されたのではないでしょうか。
『理想の返済負担率』の章でも触れましたが、おうちの悩み.com編集部では、年収は支給額ではなく手取りで計算することを推奨しています。
「計算がめんどくさい!」というあなたのために、こちらの記事では、年収別の返済可能額のシミュレーションや早見表も準備していますので、ぜひチェックしてみてくださいね!