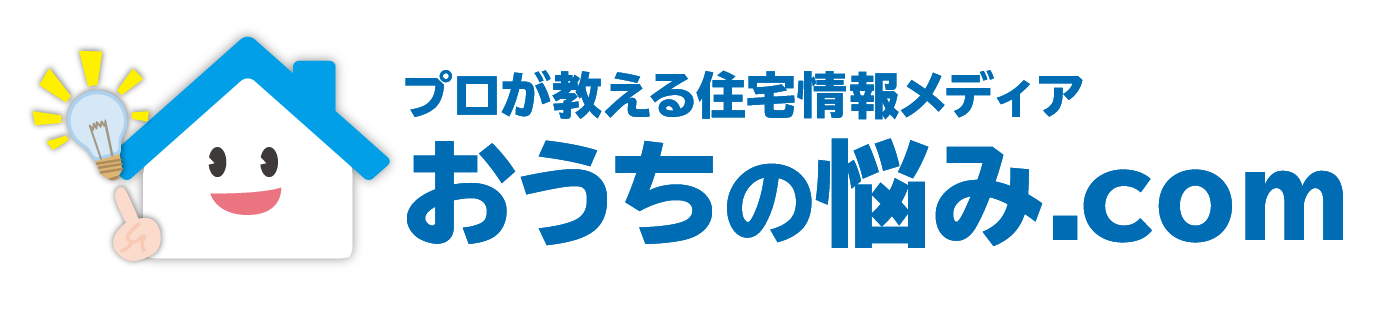一戸建ての維持費はいくら?内訳や平均費用をマンションと比較!
家の購入を検討するときは、どんな維持費があるのか事前に知っておきたいですよね。
「マンションがいいのか、一戸建てがいいのか…」と悩んでしまいます。
- 一戸建てを購入した後の、維持費の内訳を知りたい
- 各維持費のおおよその金額を知りたい
- マンションと一戸建ての維持費を比較したい
この記事では、家を購入してからの維持費を具体的にイメージできるように、内訳やおおよその金額を紹介します。
一戸建てを購入して10年経った私の経験も交えてお伝えしますので、参考にしてみてください。
購入後の支払いイメージを具体的にしておかないと、維持費が家計に重くのしかかるかもしれません。
計画的な支払いができるよう、イメージを明確にしておきましょう。
一戸建てを購入した後に必要な維持費は40~50万円!

一戸建てを購入した後に必要な維持費は、自治体によって変わりますが月40〜50万円と考えておくのが良いでしょう。
具体的には、固定資産税や都市計画税などの税金のほか、各種保険、修繕費、駐車場などその他の費用がかかるためです。
税金や保険は支払うことが分かっていますので、あまり突発性は感じません。
しかし、修繕費は築10年以降から必要となる場合が多く、また高額の場合がありますのでしっかりと積み立てておくことをおすすめします。
税金
一戸建てなどの不動産を持つと固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
毎年課税されるので、計画的に支払いができるようにしておきましょう。
固定資産税
固定資産税は、1月1日時点で家や土地などの不動産を持っている人(所有名義人)が、住んでいる市区町村へ毎年支払う税金で、金額は以下の式で計算できます。
課税標準額×標準税率1.4%
課税標準額とは、「固定資産評価額」にさまざまな軽減措置を反映させて算出される金額のこと。
固定資産評価額の計算方法はとても複雑ですが、「おおむね時価公示価格の7割程度」と覚えておくのがいいでしょう。
時価公示価格は国土交通省のウェブサイトで調べることができます。
標準税率は各自治体で決めることができ、1.4%が基本です。
それ以外の税率を設定している場合もありますので、家を建てたい市区町村の税率を調べてみましょう。
支払いについても市区町村によって違いがありますが、ほとんどの場合が以下のようなケースに当てはまります。
- 一括支払いまたは年4回の分割支払い
- 納税通知書が届くのは4〜6月
家を建てたい市区町村の支払い時期などを調べてみましょう。
都市計画税
都市計画税は、市区町村が定める『市街化区域内』に土地や建物を所有している場合に課税される税金です。
「市区町村名 市街化区域」で検索しても調べられない場合は、役場の都市計画を担当している部署に問い合わせましょう。
金額は、以下の式で算出されます。
課税標準額×制限税率0.3%
標準税率は市区町村によって異なる場合がありますが、0.3%を超えることはありません。
各種保険
一軒家の購入費用は、多くの人が住宅ローンを利用します。
住宅ローンを借りる際は各種保険への加入が必須の場合が多く、継続的に支払わなければなりません。
ここでは、各種保険に加入しなければならない理由や、保険の種類などを紹介します。
火災保険
火災保険とは、家が受けるさまざまな損害を補償する保険のことで、火災の他にも、水災や風災、盗難など広範囲を補償することができます。
また火災保険への加入は、住宅ローンを借りる際の必須条件となっていることがほとんど。
もしも金融機関が火災保険に入っていない人に融資して家が燃えてしまった場合、住宅ローンだけが残ることになり、金融機関は債権の保全ができなくなります。
その状態を防ぐために、多くの金融機関では火災保険への加入を融資の条件にしてるのです。
保険料は、家の構造や補償内容、所在地になどによって変わりますが、相場としては年間15,000円程度を考えておくといいでしょう。

地震保険
地震保険は火災保険とセットで契約します。
また、地震保険の金額や内容は各保険会社で共通。
なぜなら、地震保険は国と各保険会社が共同で運営している、公共性の高い保険であることがその理由です。
保険料は、火災保険と同じように家の構造や所在地によって決まります。
また、2022年10月には保険料が改定されることがすでに決まっており、全国平均で0.7%ほど値下げされる見込みです。
家を購入するタイミングで保険料にどう変化があるかを確認しておきましょう。
相場は年18,000円ほど。

家の修繕費
念願の一戸建て、大切に住んでいたとしても築年数を重ねると外装や機器類は劣化します。
土地の環境や建材、使い方にもよりますが、築10年程度でメンテナンスが必要になることが多いようです。
屋根、外壁などの外まわり
屋根や外壁などの外まわりは徐々に劣化するため、変化に気づきにくいもの。
気づいたとしても「これくらいいいか」と後回しにしたくなるかもしれません。
しかし、屋根や外壁などは外気から家を守ってくれる大切な部分で、後回しにすると修繕の範囲が広くなり、出費が大きくなる可能性も。
定期的に点検し、大きな出費になる前に修繕することが、安心・安全な家を長く保つ秘訣です。
設備機器
外まわりだけでなく、室内の床や壁、キッチンやお風呂の機器などもメンテナンスする必要があります。
床や壁などの内装は、住人が気になった時点で張り替えや修理を行えばよいため後回しにする人が多く、築20年以降にメンテナンスを行うことが多いようです。
しかし、毎日の生活に必要な機器に関しては、故障するとしばらく不便な生活をしなければなりません。
私も、築10年目でエコキュートが故障し、お湯が使えなくなりました。
お湯が出ないので、ケトルでお湯を沸かして洗い物や洗顔をしたり、近くの温泉に毎日通ったりと、とても苦労したことを覚えています。
こういった設備機器は故障しても修理が難しいケースが少なくありません。
数年前の機器はもう製造していないことが多く、交換部品を手配できないケースが多いためです。
機器によっては高額な費用が必要な場合もありますので、可能であれば設備機器のための積み立てもしておくことをおすすめします。
その他の維持費
一戸建ての維持費は、この他にも『光熱費』、『駐車場代』、『自治会費』などがあります。
光熱費の全国平均額は、二人以上の世帯でひと月21,836円。
駐車場代は場所によって大きく変わりますが、5,000円から20,000円程度でしょう。
自治会費は500円〜2,000円が一般的なようです。
私が住んでいる地域では、1ヶ月に自治会費500円+こども会費500円を年払いしています。
年払いだと少しお得になるケースもあるようです。
自治会費はゴミ捨て場の修繕や公園の遊具のメンテナンス、こども会費はイベント費用に使用されています。
マンションの維持費

続いて、マンションの場合の維持費を見てみましょう。
マンションの維持費として、一戸建てには無かった『管理費』や『修繕積立金』が必要です。
また、固定資産税も課税されますが、一戸建ての場合とは金額が変わりますので一つずつ紹介します。
管理費
管理費は、マンションの共用部分の管理に使用されるお金。
共用部分とは、エントランスや廊下など、マンションに住んでいる人みんなが使用する部分を指し具体的には、清掃やゴミの収集処理、照明の交換などに使用されます。
金額はマンションにより異なりますが、月1〜2万円程度を目安に考えおくとよいでしょう。
東日本不動産流通機構の2020年の調査によると、東京都の平均月額は13,566円でした。
一般的に、共用部分が広いマンションの管理費は高くなる傾向があります。
修繕積立金
修繕積立金は、多額の費用が必要なメンテナンス等に備えて積み立てられるお金です。
住民の快適な環境を整えるために使用される費用であるため、ほとんどのマンションで支払いを義務化しています。
外壁の塗り替えや防災設備のメンテナンスなどは、快適な生活には欠かせませんよね。
こちらも金額はマンションにより異なりますが、月1〜2万円程度が目安のようです。
東日本不動産流通機構の2020年の調査によると、東京都の平均月額は11,071円でした。
大規模な修繕が発生し積立金で足りない場合は、一時金が必要なケースもあることも覚えておいてくださいね。
駐車・駐輪費用
駐車・駐輪場を使用する場合は、利用料金が発生します。
月極駐車場検索サイト『アットパーキング』によると、同サイトに登録された月極駐車場の平均賃料は、東京都で22,592円、大阪府で12,278円です。(2021年7月時点)
駐車場、駐輪場は毎日使用するものなので、使い勝手を考えながら毎月の支出計画に組み込む必要があります。
固定資産税
マンションでも固定資産税の支払い義務は発生します。
ただ、実際に支払う金額は一戸建てよりもマンションの方が安くなるケースが多いです。
というのもマンションの場合、土地に関する税額は敷地に対する割合によって按分した金額となるため。
一方、建物に関する税額は一戸建てよりもマンションの方が高くなる可能性があります。
なぜなら、多くのマンションは鉄筋コンクリートのため、木造が多い一戸建てよりも評価額が高くなる可能性があるためです。
土地と建物両方の固定資産税の金額を合計すると、一戸建ての方が高いケースが多いといわれています。
一戸建ての方が維持費が安いケースが多い

もちろん、立地条件や環境などにもよりますが、一般的に一戸建ての方が維持費が安いケースが多いです。
これまで紹介してきた費用を、30年間支払い続けたと想定して比較してみましょう。
| 一戸建て | マンション | |
| 固定資産税※1 | 300万円 | 240万円 |
| 都市計画税 | – | – |
| 火災保険※2 | 24万円 | 12万円 |
| 修繕費※3 | 約425万円 | – |
| 管理費・修繕積立金※4 | – | 約877万円 |
| 駐車・駐輪費用 | – | – |
| 合計 | 約749万円 | 約1,129万円 |
※1 一戸建て=年10万円、マンション=年8万円で想定
※2 一戸建て=10年8万円、マンション=10年4万円で想定
※3 不動産情報サービスアットホーム株式会社の調査一戸建て修繕の実態より
※4 東日本不動産流通機構首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金より
今回の試算では、マンションの方が30年間で約380万円高くなりました。
表にしてみると、『管理費・修繕積立金』がマンションの維持費の大部分を占めていることがわかりますね。
一戸建ての場合は、自分のタイミングで修繕を決めることができますが、マンションだと毎月決まった金額を支払う必要があるため、維持費としてじわじわとかさんできます。
維持費を節約する方法

一戸建てを購入するには欠かせない維持費を、少しでも節約する方法を紹介します。
毎日のお手入れなど、自分でもできることがたくさんありますので覚えておいてくださいね。
耐用年数の長い建材を選ぶ
外壁や屋根に耐用年数が長い建材を選ぶと、メンテナンスにかかる費用を抑えることができます。
外壁であれば、タイル材のほか金属系や樹脂系のサイディングなど、屋根材は、日本瓦や鋼板、ガルバリウム鋼板がおすすめ。
ものや状態によっては、50年以上の耐用年数が期待できるものも!
とはいえ、いずれの素材も、全くメンテナンスが不要なわけではありません。
また、耐用年数が長い素材はその分高額ですので、購入時の予算と相談しながら決めていくのがいいでしょう。
こまめな点検・お手入れを行う
維持費を節約するには、自分でできることもあります。
例えば、定期的に自分の目で家の状態を点検することもメンテナンスのひとつです。
屋根や外壁に異常がないかサッシの継ぎ目部分などにひび割れがないかなどをチェックすることで早期発見につながります。
異常を早く発見し、修繕箇所が小さいうちに直してしまえば、その分修繕費用を抑えることができますよね。
はじめは、家を建てた住宅メーカーで定期的に点検してくれるかもしれません。
しかし、それに頼りっきりにならずに、利害関係のない第3者から見てもらうのもいいでしょう。
また、こまめなお掃除も立派なメンテナンスのひとつ。
特に水回りはカビが発生しやすく、劣化が進行しやすい場所です。
放置して汚れがひどくなると、どんどん掃除をしたくなくなってしまうもの。
ラクにお掃除できる道具もたくさんありますので、こまめにお掃除しましょう。
換気も簡単にできるお手入れのひとつです。
湿気を含んだ空気は、カビの発生や木材の腐食の原因になるなど、家にとっては大敵。
天気の良い日は窓を開けて意識的に換気をしましょう。
高機密住宅では24時間換気システムが標準装備されていますが、寒いからといって止めてはいけませんよ。
固定資産税の控除を利用
固定資産税は、条件によってさまざまな控除を受けられますので、一部紹介します。
他にも減額措置はたくさんありますので、自分がどのような家を建てるかを想像しながら調べてみてくださいね。
減額措置
2024年3月31日までに建てられた新築の建物は、次のとおり減税されます。
- 戸建て:1/2減額(3年間)
- マンション:1/2減額(5年間)
減額措置を受けるには、各市区町村役場への申請が必要です。
住宅用地の特例
固定資産税は土地と建物それぞれに課税されます。
『住宅用地の特例』は、住宅用地として認定された土地に対して、課税標準額が軽減される特例です。
住宅用地の申請は各区町村の役場に提出します。
減税額は次の通りです。
- 住宅1戸につき200㎡以下の部分=課税標準額が1/6
- 住宅1戸につき200㎡を超える部分=課税標準額が1/3
そのほかにも長期優良住宅に認定されると受けられる特例など、条件によって固定資産税が減額となるさまざまな減額措置があります。
4-4.火災保険の比較・見直しを行う
火災保険は、金融機関から住宅ローンの融資を受ける際、加入が必須条件です。
そのため、補償内容を確認せずに加入する人も多いかもしれません。
だからこそ、自分に合った補償内容か確認することが維持費の節約につながります。
例えば川や海から離れている場所であれば、水災補償は必ずしも必要とはいえないかもしれません。
同じ補償でも他に安い会社やプランがないか、定期的な見直しをしましょう。
まとめ
家を購入した後の、維持費について紹介してきました。
マンションと一戸建てでは支払う維持費も違い、長い期間で見ると最終的に支払う金額も変わるでしょう。
今回ご紹介した内容も、市区町村によって違ったり、改定があったりと変わることがあります。
実際に住んでから、「計画になかった出費が辛い…!」といった状況になるのは避けたいもの。
いざという時大きな負担とならないよう、少しずつ積み立てておきましょう!
住宅建築アドバイザーに相談するのも一つの方法
ハウスメーカーは、各社それぞれが素敵な提案をしてくれます。
そのため、考えれば考えるほどどの会社が本当にいいのかわからず、迷ってしまう方も少なくありません。
そんな方には、「SUUMO」が提供している建築会社選び講座がおすすめ。
住宅建築アドバイザーがあなたのライフスタイルや状況などを聞き、フラットな目線で総合的な判断をしたうえで無料で会社選びのコツを教えてくれます。
- 維持費の抑えた家を建てる方法は?
- ハウスメーカーと工務店どっちがいい?
- 建築会社はどうやって選べばいいの?
- 理想の家を建ててくれる建築会社を見つけたい!
- 第三者の目線でアドバイスが欲しい
- カタログやインターネットだけでは判断できない
どれか1つでも当てはまる方にはオススメできる講座です。
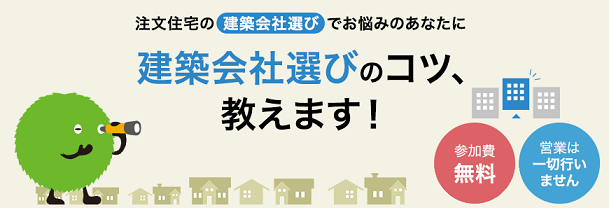
全国に80か所以上ある店舗か、インターネットを使って自宅でも受講できます。
プロの目線から本当にあなたに合った会社を紹介してもらうこともできます。
完全無料で、個別相談に対応してくれるので、本気で良い家を建てたい方は是非チェックしてみてくださいね!
マイホームづくりは、くれぐれも慎重に…
| この記事の監修:嵯峨根 拓未 所有資格:宅地建物取引士 |