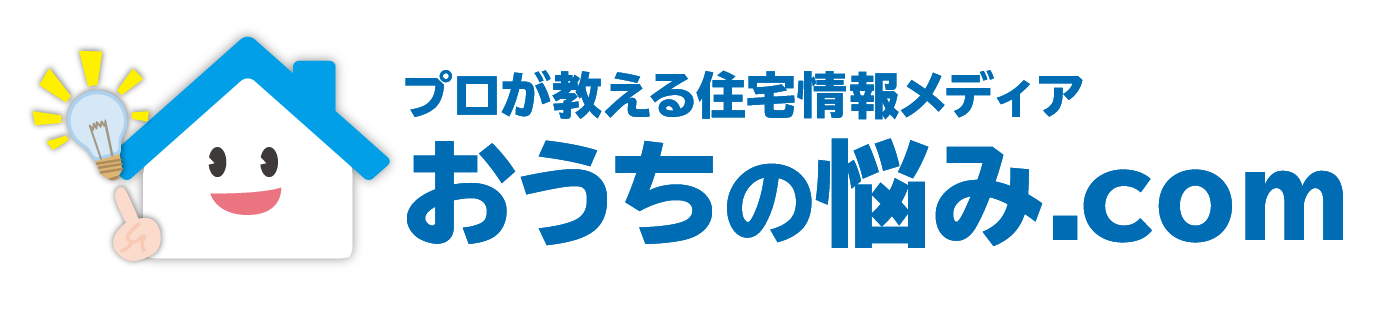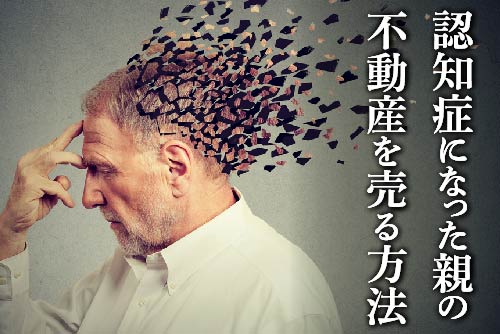認知症になった親の家を売りたい!成年後見制度を利用する7ステップ
「人生100年時代」に突入した日本。
高齢者の4人に1人が認知症またはその予備軍といわれています。
「親が認知症で施設に入るため、親の不動産を売却したい」という方も増えています。
認知症の親の代わりに家を売るには「成年後見(せいねんこうけん)制度」を利用します。
家族だからといって勝手に処分したり、正しい方法を知らずに売却すると、施設に入ってから「売買契約の取り消し!」・・・なんてことになってしまいます。
この記事では、認知症の親の代わりに不動産を売る方法をわかりやすく解説します。
正しい流れを理解して、スムーズに不動産売却していただければと思います。
★今すぐ7ステップを見る方はコチラ
認知症になると不動産売却できない
・不動産売却できるのは名義人のみ ・意思能力がないと不動産売却できない
不動産売却には2つの原則があります。
たとえ血のつながった子供でも、名義人以外が不動産を売ることはできません。
名義人本人が認知症になってしまった場合も売却できません。
- 不動産を売るとどんな結果になるのか?
- 売却にともなって発生する納税義務を理解しているか?
本人がこのようなことが分からない状態であれば、売買契約は無効となります。
成年後見制度とは?

不動産売却の2つの原則にしたがうと、名義人が認知症になったら一生不動産売却できないことになりますよね。
そこで登場するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、判断能力がない人に代わり「後見人」が法的契約をおこなう制度です。
成年後見制度は2種類
成年後見制度には、2つのタイプがあります。
1.法定後見制度
法定後見制度は、すでに認知症を発症しているときに利用します。
裁判所が後見人にふさわしい人を選ぶので、子供が代理人に立候補しても認められないこともあります。
法定後見人はさらに3つに分類されます。
- 後見人…本人の判断能力がまったくない
- 保佐人…本人の判断能力が著しく不十分
- 補助人…本人の判断能力が不十分
後見人にはほとんどの代理権が与えられ、保佐人・補助人には制限付きの代理権が与えられます。
2.任意後見制度
一方、任意後見制度は、まだ認知症を発症していないときに利用できます。
本人が「将来、私が認知症になったらこの人を代理人にします」とあらかじめ後見人を指名しておく方法です。
後見人にどのような手続きを任せるのか親が自分で決め、「任意後見契約」を結んで公正証書を作成します。
ただし、任意後見制度にはデメリットもあります。 ・取消権がない ・契約書に記載された代理権のみ
取消権とは、すでに結んだ契約を無効にすること。
たとえば、認知症の親が高額なリフォーム契約をしてしまったとき、法定後見制度であれば契約を取り消せます。
しかし、任意後見制度を利用した場合はあきらめてリフォーム代を支払うしかありません。
また後見人は、公正証書に書かれた限定的な手続きしかおこなえません。

成年後見制度は裁判所の許可が必要
認知症になっても、自動的に後見人がつくわけではありません。
裁判所に申し立てをし、「この方には成年後見人が必要ですね」と認めてもらうことで、はじめて成年被後見人になれます。
代理人についても「この方になら管理を任せられそうですね」と裁判所に認めてもらうことで、成年後見人になれます。
成年後見人になれる人
裁判所は、後見人候補者の職業・経歴をチェックし、成年後見人にふさわしい人を選びます。
後見人として認められるのは、以下に当てはまる人です。
上記からわかるように成年後見制度は、面識のない他人が親の財産管理をする可能性もあります。
また成年後見人が複数人になったり、成年後見人がきちんと任務をしているかチェックする「成年後見監督人」がつくケースもあります。
成年後見人になれない人
認知症の親に24時間付きそって世話をしていても、以下の人は成年後見人にはなれません。
財産を管理する法的効力がない人、社会的信用のない人は裁判所に選ばれることはありません。
成年後見人の7割は専門職
親族が後見人に立候補しても、実際に選ばれるのは弁護士などの専門職が7割です。
特に、以下のケースでは第三者が選ばれやすくなります。
しかし「成年後見制度の利用の促進に関する法律(2016年)」が施行され、最高裁判所は「後見人にふさわしい親族がいる場合、本人の利益保護のために親族を選任することが望ましい」と発表しました。
これにより、今後は親族も成年後見人に選ばれやすくなっていくでしょう。
成年後制度にさらについて詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
成年後見人の義務と権利

成年後見人になると、不動産売却をおこなう権利を得ると同時に、さまざまな義務も生じます。
成年後見人の任務は本人が亡くなるまで
成年後見人は、認知症の本人が亡くなるまで財産を管理し続ける義務があります。
不動産売却後も、家庭裁判所に財産状況について定期的に報告しなければなりません。
財産処分は正当な理由が必要
後見人にはさまざまな権利がありますが、本人の財産を処分する場合は「本人の利益のために使う」という正当な理由が必要です。
あくまでも、本人の利益のために処分というのが前提です。
たとえば、不動産価格について「どうせ本人は分からないから」と著しく低い価格で売ってしまうと、「本人の不利益」にあたり売却が認められないこともあります。
居住用不動産の売却には許可が必要
さらに居住用不動産を売る場合には、家庭裁判所の許可の必要です。
- もともと親が住んでいた家
- 退院後に戻る予定の家
- 将来的に住む可能性がある家
居住用の認識を間違え、裁判所の許可を得ずに売却すると売買契約が取り消されてしまうので注意してください。
認知症…?グレーなときの対処法

年齢のせいなのか認知症なのかよく分からないときは、まずは医師の診断を受けてください。
意思能力による3つの売却パターン
親の意思能力の程度によって、3つの売却パターンに分かれます。
①意思能力が正常⇒「委任状」
- 病気で入院中
- 体が衰え、施設に入っている
体が不自由でも、本人の意思がハッキリしている状態なら「委任状」を作成し、代理人として不動産売却ができます。
これがもっとも簡単な方法です。
②意思能力がない⇒「成年後見制度」
- 自分の生年月日が分からない
- ここがどこかも分からない
体は元気でも、明らかに認知症と分かる状態のときは「成年後見制度」を利用します。
③軽度の認知症⇒「委任状」または「任意後見制度」
- 日常会話はできる
- 記憶があいまいなときもある
認知症の初期段階であれば、本人の意思能力があるうちに「委任状」または「任意後見制度」を利用できる可能性があります。
ただし、医師の診断と司法書士の判断が必要です。

司法書士には「有効な売買契約か?」を確認する法的責任があるため、身内が勝手に委任状を作成し、売却することはできません!
認知症チェックリスト
東京都の発表しているこちらのチェックリストも参考にしてみてください。
【認知症チェックリスト】
- 財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることがある
- 5分前に聞いた話を思い出せないことがある
- いつも同じ事を聞くなどのもの忘れがある
- 今日が何月何日かわからないときがある
- 言おうとしている言葉がすぐに出てこないことがある
- 貯金の出し入れや、家賃や公共料金の支払いが一人でできない
- 一人で買い物に行けない
- バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できない
- 自分で掃除機やほうきを使って掃除ができない
- 電話番号を調べて電話をかけることができない
引用:東京都福祉保健局「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」
※このチェックリストはおおよその目安であり医学的診断に代わるものではありません。また身体機能が低下している場合はチェック項目が多くなる場合があります。
チェック数が多いほど認知症の可能性が高いといえます。
この他にも「長谷川式認知症スケール」という、簡単な計算問題や記憶力のテストもあります。
司法書士が意思確認を行うときは、まったく関係のない書類を見せ「この不動産で間違いないですか?売却してもいいですか?」とたずね、正しく訂正できるかチェックすることもあります。
成年後見制度を利用して親の家を売る7ステップ

成年後見制度を利用して、不動産売却する方法を説明します。
成年後見申し立ての7ステップ
①家庭裁判所に申し立てをする
本人の住所を管轄する家庭裁判所に「成年後見制度開始」の申し立てをします。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。
②家庭裁判所による調査と審理
家庭裁判所から依頼された医師が、本人の意思能力の評価と診断書を作成します。必要な場合は鑑定も行います。
さらに家庭裁判所の調査官が、申立人・本人・後見人候補者からくわしい話を聞きます。
その際、親族照会で親族同士の争いごとなどがないかもチェックされます。
③後見人選定と審判確定
家庭裁判所が法定後見人にふさわしい人を選び、後見開始の審判を確定します。
申し立てからここまで3ヵ月ほどかかります。
④不動産業者と媒介契約をして買主を探す
不動産会社と媒介契約を結び、買主を探します。
不動産会社選びは慎重に行ってください。
⑤「居住用」不動産なら家庭裁判所の許可を得る
居住用不動産を売却する場合は、裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を行います。 【居住用不動産処分許可申立の必要書類】
こういう人に、いくらで売りますがよろしいですか?と裁判所にお伺いをたてるということです。
裁判所の許可を得ずに売却すると、売買契約は無効になるので注意してください。
⑥買主と売買契約を締結する
家庭裁判所の許可がおりたら、正式な売買契約を結びます。
「裁判所の許可がおりたら契約の効力が発生する」という特約をつけ、先に売買契約を結んでおくケースもあります。
⑦代金精算と所有権移転登記
売却代金を受け取り、所有権移転登記と引き渡しをおこないます。
売却代金はすべて親の口座に振り込まれます。
親以外の口座に振り込むと、振り込まれた人が横領したと見なされてしまうため注意してください。
成年後見申し立ての必要書類
成年後見申し立て時に必要な書類は、以下のとおりです。 【申立の必要書類】
本人の意思能力の程度によって必要書類は異なります。
住所地を管轄する裁判所または司法書士に確認してください。
申し立て費用
成年後見制度の申し立て費用の内訳は以下のとおりです。
このほかに必要書類の取り寄せにかかる実費、医師の鑑定を受ける場合の鑑定料(5~10万円程度)、弁護士・司法書士報酬が発生します。
手数料以外の費用は人によって異なるので、まとまった資金を用意しておくと安心ですね。
成年後見人に毎月報酬を支払う
弁護士や司法書士が成年後見人になった場合は、成年後見報酬として毎月の報酬を支払うことになります。
報酬は、管理する財産額によって異なります。 ・財産額1,000~5,000万円…月額3~4万円 ・財産額5,000万円以上…月額5~6万円
この支払いは親の財産から捻出することになります。
ボランティアの市民後見人もいる
報酬を支払う財産がない場合は、市民後見人にお願いすることができます。
市民後見人とは、一般市民がボランティアで認知症の方の後見人になることです。
報酬は発生しないので、費用がなくても安心して利用できます。
市民後見人は、自治体が実施する研修を受講し、専門家のバックアップを受けながら、後見人としての任務を行います。
厚生労働省の調査によると、このような「市民後見推進事業」を実施している自治体は、36都道府県(158市区町)あります。
また、8割の市町村では成年後見制度の助成制度があるので、ぜひ自治体に相談してみてください。
後見人が知っておきたい「利益相反」
後見人が知っておくべき知識に「利益相反」というものがあります。
ある日、弟が病気で意思能力を失ったため、兄が後見人になりました。
のちに父親が亡くなり、兄弟で遺産を分け合うことになりました。
このとき兄は「弟の後見人」でもあり、「遺産を受け取る相続人」でもあります。
すると、兄が遺産を多くもらい、弟が損をするような遺産分割協議が成立してしまいます。
このようなケースを「利益相反」と言い、利益相反となる行為は法律によって禁止されています。
上記のケースの場合、兄の選択肢は3つです。
2.後見監督人がいる場合、後見監督人が遺産分割協議をする
3.後見監督人がいない場合、「特別代理人」を選任する
遺産を受け取るためには、自分以外の人に遺産分割協議をしてもらうということです。
「特別代理人」とは、1つの事案のためだけに任務を行う代理人のこと。
この例でいうと「遺産分割協議をし、兄弟に公平に遺産を分配したら任務完了」です。
まとめ
いかがでしたか?
親が認知症になった場合は「成年後見制度」を利用した不動産売却できます。
成年後見人になると、不動産売却をしたあとも、本人が亡くなるまで後見人としての義務がつづきます。
申し立てから売却できるまでは3ヵ月かかるので、売却を急ぐ場合は、裁判所の手続きと同時に不動産売却の準備も進めておくことをおすすめします。
弁護士や司法書士と連携している不動産会社を選べば、成年後見人の手続きから不動産売却まで一貫したサポートを受けられます。
信頼できる不動産会社を選ぶなら、複数の不動産会社を一度に比較できる不動産一括査定サイトがオススメです。
こちらの記事でぜひチェックしてみてください。
プロが勧める不動産一括査定サイト5選!口コミ・メリットデメリットも解説!
この記事があなたのお役に立てれば幸いです!