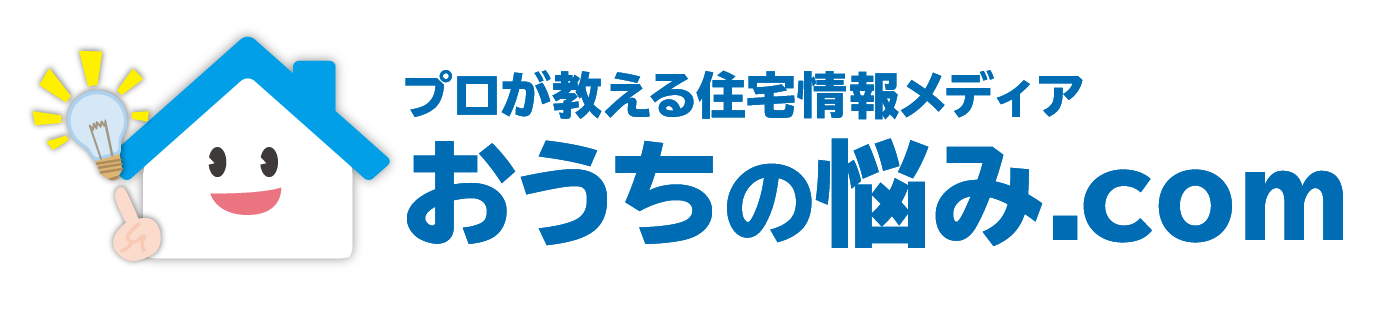【不動産売却のトラブル事例】解決策や困ったときの相談先はどこ?
不動産を売却するとき、いくら高く売れてもトラブルに巻き込まれるのは絶対に避けたいですよね!
- どんなトラブルが多いの?
- トラブルを防ぐ対策は?
- 新生活をストレスなく楽しみたい!
大きなお金が動く不動産売却には多少のトラブルはつきものです。
普段は温厚でも、数千万円のお金が絡むと人が変わることもあります。
売却した後に、買主から損害賠償請求をされたら大きなストレスを抱えることになってしまいますよね。
トラブルに巻き込まれないためには、過去のトラブル事例を知っておくことが有効です。
この記事では、不動産売却のトラブル事例と解決策、困ったときの相談先をご紹介します。
思いっきり新生活を楽しむために、是非ご覧ください!
不動産売却のトラブルの原因
1.伝達不足 2.確認不足
不動産売却でトラブルが起こるほとんどの原因は次の2つです。
「なんだそんな簡単なことか」と思われるかもしれませんが、不動産売却で伝達と確認をもれなくやるのは意外と難しいんです。
なぜなら、人と人との取引ではこんなふうに考えてしまいがちだからです。
「意味がよく分からないけど後で調べればいいや」(確認不足) 「面倒くさい売主だと思われたくない」(伝達不足/確認不足)
「わざわざ言わなくても分かるだろう…」(伝達不足)
さらに、不動産取引にはこんな特徴もあります。
- 専門性が高い
- 取引価格が高額
- 売主・買主の事情がバラバラ
ほとんどの人が不動産売買に不慣れで、何が重要なのかも分かりにくいため、認識の違いによるトラブルが起きやすくなります。
「営業担当に任せているから大丈夫」と思っていても、売主に不利な条件を契約書にしれっと盛り込む業者もいます。
トラブルに巻き込まれないためには、伝達と確認を怠らず、自分の身は自分で守るスタンスを貫いてください。
不動産トラブルの7割は売買によるもの
不動産の売買・賃貸における苦情件数は年間1,748件。そのうちの7割は不動産売買によるトラブルです。(国土交通省「宅地建物取引業法の施行状況調査結果」2019年3月)
いつトラブルに巻き込まれてもおかしくない数字なので、万全な対策が必要になります。
特に、中古物件の売買でのトラブル率が高く、圧倒的に多いのは土地・建物の欠陥についての苦情。
次いで、契約解除、不動産会社からの報酬請求によるトラブルが多くなっています。
よく起こるトラブル事例7つ
不動産売買のトラブルは、そのほとんどが契約した後に起こるため、売却したからといって安心できません。
一体どんなトラブルが起こるのか?不動産売却で実際に起こったトラブル事例をご紹介します。
雨漏りが見つかり損害賠償を請求された
補修代金と損害賠償を請求された。
不動産売買では、売主に「瑕疵担保責任」があり、売却後に隠れた欠陥が見つかったときは(売主が知らなかった欠陥であっても)売主の責任になります。
瑕疵に当たるのは以下の問題です。
物理的瑕疵
- シロアリ被害
- 雨漏り
- 給湯器などの設備故障
- 柱や梁などの構造耐力不足
- 有害物質を含む建材の使用
- 断熱材不足
- 地中の埋設物
- 地盤沈下
- 土壌汚染
心理的瑕疵
- 過去に事故や火災があった
- 過去に人が亡くなっている
法律的瑕疵
- 再建築不可
- 建築制限で自由に土地を利用できない
環境的瑕疵
- 近隣の騒音や振動
- 高層ビルの建設予定による日照障害
- 近隣にゴミ処理施設がある
- 近隣に暴力団事務所や宗教団体施設がある
大きなトラブルに発展しやすいのは、売主が欠陥について知っているのに告知しなかったときです。
買主は「知っているなら言ってほしい!騙された!」という気持ちになるため、多額の損害賠償請求をされたり契約解除を求められることもあります。

【関連記事】
▶【不動産売却】売主が知っておくべき「瑕疵担保責任の基礎知識」
エアコンを返してほしいと要求された
しかし、買主はエアコンが付いているものだと思っていたため、入居後にトラブルになった。
不動産売買の契約時は「付帯設備表」を作成して、エアコンや給湯器などの引き継ぎについて取り決めをします。
引き継ぐ物に“エアコン”と記載されていれば、返却または売主の負担で新しいものを取り付けなければなりません。
その他にも、インターホンや照明をどうするか取り決めをしていなかったり、設備の故障を告知していなかった場合もトラブルが発生しやすくなります。

一方的に契約を解除された
違約金は払ってもらえるのか?
買主の都合で契約を破棄するときは売主は手付金を没収することができきます。
さらに、手付解除の期日を過ぎていれば違約金も請求できます。
ただし「住宅ローン特約」がある場合で、買主のローンが通らなかったときは契約は白紙となり、手付金を全額返還しなければなりません。
その際は、不動産会社への仲介手数料の支払いはありません。

この点で不動産会社とトラブルになるケースも多いので、媒介契約時に仲介手数料の支払い条件についてよく確認しておいてください。
マンションのリフォームができないとクレーム
これに対して「事前説明がなかった」とトラブルになった。
不動産売却をするときは、契約前に買主に重要事項事項を説明する義務があります。
重要事項説明書に「リフォーム時は近隣入居者の承諾が必要」と記載されたマンション規約があれば、買主は了承した上で購入したことになります。
その場合、売主に責任はありません。
その他にも、ペット不可、楽器不可、バルコニーに布団を干すのは不可など、細かい決まりを買主が把握していなかったためにトラブルになるケースも多いです。

別荘の売却依頼で広告費を請求された
すると「広告を出すので50万円を至急振り込んで欲しい」と言われた。
媒介契約時に、「広告費用は売主の負担」という契約を結んでいなければ、広告費を支払う必要はありません。
ただし「遠隔地の物件を売却するための旅費」としての現地案内費用などは、請求が認められる場合もあります。

コンサルティング料金を請求された
媒介契約書に定められている仲介手数料以外に、コンサルティング料金を支払う必要はありません。
「御社とコンサルタント契約は結んでいません。仲介手数料で十分なはずです。」と断ってください。
たまに、仲介手数料を無料にする代わりに、高額なコンサルティング料を請求する悪徳業者もいます。
このような高額報酬の請求は、宅地建物取引業法に違反する可能性があります。

媒介契約を自動更新された
しかし「媒介契約は自動更新なので変更できない」と言われた。
国土交通大臣が告示している「標準媒介契約約款」に基づいた契約である限り、媒介契約の自動更新はできません。
標準約款に基づく契約は、契約期間最長3ヵ月、契約更新は売主が申し出た場合のみ可能となっています。
媒介契約書に「自動更新」の規定を盛り込むのであれば「標準約款に基づく契約ではない」と明記しなければなりません。
この記載がないのに自動更新の規定があったり、標準約款に基づいた契約なのに契約更新を強制することはできません。

トラブルになったときの解決策

万が一トラブルになってしまった場合は、長引かないようにできる限り早く解決することが大切です。
スムーズに解決するための方法をお伝えします。
契約内容を再確認する
トラブルが起きたら、まずは契約書を隅々まで確認してください。
特にトラブルに関係する項目は熟読して、言葉の意味をしっかり理解することが第一です。
署名・捺印のある契約書に基づいて、話し合いをしていくことになります。
メモや録音をする
話し合いでは「言った」「言わない」というさらなるトラブルを避けるため、記録をとるようにしてください。
特に、契約書に記載がないことについて、いつ、どこで、誰が、何を言ったかは重要な証拠になります。
また、メモや録音をすることで感情的なやり取りが減り、解決につながりやすくなります。
記録は書面にして相手方と共有し、いざというときに第三者に提出できるようにしておくのがベストです。
こじれてしまったら相談窓口へ
話し合いがこじれてしまうと、当事者同士での解決は難しくなります。
特に、相手がプロの不動産会社の場合は、知識の少ない一般の売主はどうしても不利になってしまいます。
そのようなときは、早めに以下のような第三者機関に相談をしてください。
取引をした不動産会社が所属する団体の相談窓口
- 全国宅地建物取引業協会連合会(全国宅地建物取引業保証協会)
- 全日本不動産協会(不動産保証協会)
- 日本住宅建設産業協会
- 不動産流通経営協会
国や都道府県の相談窓口
- 国土交通省の地法整備局
- 都道府県庁の相談窓口
専門家
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 土地家屋調査士
- 測量士
消費生活センター・国民生活センター
一般財団法人不動産適正取引推進機構
都道府県や業界団体で手に負えなくなった紛争の調整、仲裁を行う機関
(行政庁や消費生活センター経由での依頼になる)
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行う機関
相談をするときは、トラブルの経緯を客観的かつ冷静に話してください。
また、裁判をしたいのか?示談にしたいのか?どうすれば納得できるのか?など「あなたはどうしたいのか?」という意思を明確にした上で相談するようにしてください。
まとめ
いかがでしたか?
不動産トラブルの原因は次の2つです。
- 伝達不足
- 確認不足
また、不動産会社に任せっきりにするのではなく、自分の身は自分で守るというスタンスを貫いてください。
- 契約書の内容をしっかり確認する
- 伝えるべきことは伝える
- 分からないことはその場で確認する
小さなことでも丁寧に確認していくことが大切です。
あなたがトラブルのない新生活を送るお役に立てれば幸いです!